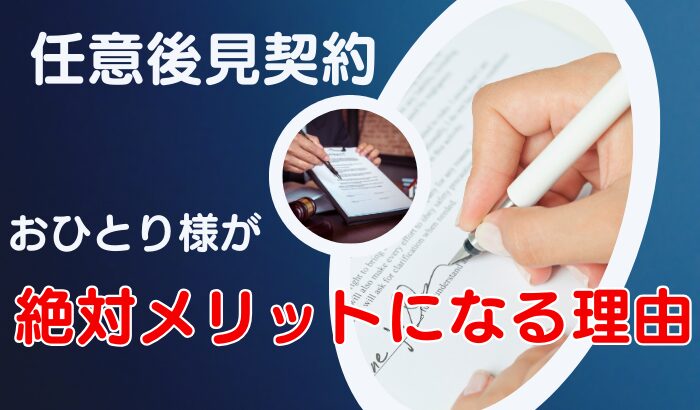
成年後見人は、ニュースでなんとなく
聞いたことがあるかもしれません。
意味は分からず、自分に関係がないと
今までは思ってきたと思います。
任意後見契約を調べないにしても
終活を検索しているうちに
出てきた言葉なのではないでしょうか?
とくに一人暮らしで今後の生活に
不安を抱いている人にとって
頼れる家族や親族がいなく
知り合いもいない人にとっては
大変頼れる制度になります。
自分の認知機能が怪しくなって
来た時に大活躍してくれるものに
なります。
さらに詳しく任意後見契約に
ついて見ていきましょう。
スポンサーリンク
任意後見契約とはどういうものなの?

自分で精神状態や認知機能が正常なうちに
認知症や障害の場合に備えて
あらかじめ本人自らが選んだ人
(任意後見人)に
代わりにしてもらいたいこと
(金銭管理・不動産・財産管理等)
を契約(任意後見契約)で決めておく
制度です。
もし、任意後見契約をしていない時に
自分が認知症になり
物事の判断ができなくなってしまった場合
公的に裁判所が成年後見人を指名します。
任意後見契約をするにはどういう状態の時にするの?
本人がまだ精神的にも
健全に物事が判断出来る時に
自分が選んだ人と任意後見契約
できます。
契約時は、公証役場で公証人が
作成した書類で契約を
結ぶものとされています。

任意後見契約は誰にお願いすればいいの?

任意後見契約は、家庭裁判所から
任意後見監督人として
選任されます。
家庭裁判所が、任意後見人として
ふさわしくないと
判断されるような事由がない限り
成人であれば誰でも任意後見契約人に
なれます。
スポンサーリンク
任意後見契約を申請するにはどうしたらいいの?
申立人
– 本人(任意後見契約の本人)
– 配偶者
– 四親等内の親族
– 任意後見受任者
申立先
– 本人の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
– 申立手数料 収入印紙800円分
– 連絡用の郵便切手(申立てされる
家庭裁判所へ確認してください。)
– 登記手数料 収入印紙1,400円分
(すでに登記印紙1,400円分をお持ちの方は
当分の間、それによって納付していただく
こともできます。)
– 本人の精神の状況について鑑定をする
必要がある場合には、申立人にこの鑑定に
要する費用を負担していただくことがあります。
申立てに必要な書類
- 申立書
- 標準的な申立添付書類
- 本人の戸籍謄本(すべて事項証明書)
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
法務局・地方法務局の本局で発行するもの。
取得方法や、証明申請書の書式等に
ついては法務省のホームページを
ご覧ください。 - 本人の診断書
家庭裁判所が定める様式のもの。 - 本人の財産に関する資料
不動産登記事項証明書(未登記の場合は
固定資産評価証明書)、預貯金および
有価証券の残高がわかる書類
(通帳写し、残高証明書等)等)
・任意後見監督人の候補者がある場合には
その住民票または戸籍附票
任意後見監督人の候補者が法人の場合には
当該法人の登記事項証明書
- 同じ書類は1通で足ります。
- 審理のために必要な場合は
追加書類の提出をお願いすることが
あります。
また、申立時に申立書のほか
各家庭裁判所が定める書式
(財産目録、収支予定表、事情説明書等)
に記入していただくこともあります。
任意後見契約公正証書の作成に
必要な費用について
作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
その他
ご本人らに交付する正本等の証書代
登記嘱託書郵送用の切手代など
任意後見人の基本的な仕事内容
任意後見契約は、委任者が自分の生活
療養看護や財産管理に関する事務について
任意後見人に「代理権を与える契約」です。
任意後見人の仕事は、この与えられた
代理権を用いて行うものです。
- 委任者の「財産の管理」
- 自宅等の不動産や預貯金等の管理
- 年金等の受取
- 税金や公共料金の支払
- 「介護や生活面の手配」
- 要介護認定の申請等に関する
諸手続 - 介護サービス提供機関との
介護サービス提供契約の締結 - 介護費用の支払
- 医療契約の締結
- 入院の手続
- 入院費用の支払
- 生活費を届けたり送金したり
する行為 - 老人ホームへ入居する場合の
入居契約を締結する行為
以上のように、任意後見人の仕事は
委任者の財産をきちんと管理し、
介護や生活面のバックアップをすることです。
なお、任意後見人の仕事は、代理権を
用いて行うものであり、任意後見人が
自分で被後見人のおむつを替えたり
掃除をしたりするという事実行為をすることでは
ありません。
- 要介護認定の申請等に関する

任意後見契約になる場合
任意後見契約は、候補者一人で
決めることはありません。
たとえば、ケアマネやペルパー
市の職員や、社会協議会などその人に
関わっている組織の方が認知症
などが進行してきてお金の管理などが
できなくなってきた時に家庭裁判所に
申立をすることで
裁判所から任命され任意後見契約活動を
スタートすることができます。
まとめ
私たちは確実に歳をとり、確実に
物事の判断能力が衰えてきます。
高齢者のうち、認知症高齢者は
平成24年時点では約462万人
そのうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」
Ⅱ以上の認知症高齢者は約305万人と
推定され年々増加しているとみられています
(厚生労働省ホームページ)。
そして、年々増える一人暮らし世帯
イコール身寄りがない人が
増加していることで任意後見契約や
成年後見人を依頼するケースが
増加していくと考えられています。
この任意後見契約制度も終活の
ひとつですので、一人暮らしの方は自分が判断
できなくなる前に早めに任意後見契約を
依頼しておくのが大切です。
後で後悔する前に、きちんと自分で
計画を立てて終活をしていきましょう。

PONO那覇がお手伝いをします。
スポンサーリンク


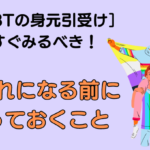


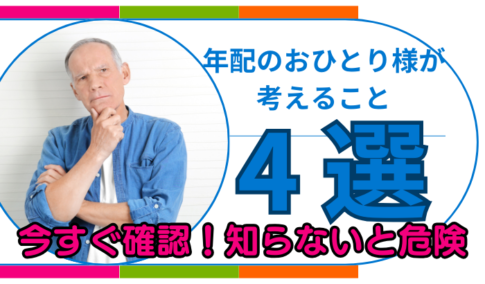

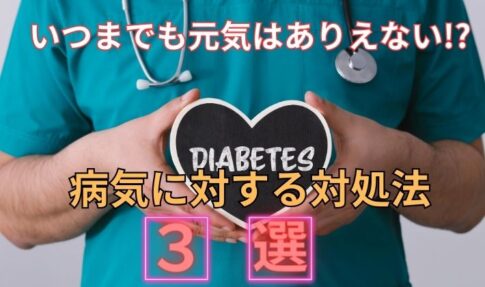



 Users Today : 4
Users Today : 4 Users Yesterday : 4
Users Yesterday : 4 Users Last 7 days : 47
Users Last 7 days : 47 Users Last 30 days : 174
Users Last 30 days : 174 Users This Month : 151
Users This Month : 151 Users This Year : 1071
Users This Year : 1071 Total Users : 1710
Total Users : 1710 Views Today : 4
Views Today : 4 Views Yesterday : 5
Views Yesterday : 5 Views Last 7 days : 159
Views Last 7 days : 159 Views Last 30 days : 727
Views Last 30 days : 727 Views This Month : 650
Views This Month : 650 Views This Year : 4688
Views This Year : 4688 Total views : 7281
Total views : 7281 Who's Online : 0
Who's Online : 0
コメントを残す