
2025年には、団塊の世代の方がすべて
後期高齢者になり5人に1人は認知症になると
言われています。
日本には、病気により自分で判断に
心配がある人のために法律で成年後見制度が
制定されておりあなたが自身で物事の
判断が不安で心配になった時
制度でサポートしてもらえます。
成年後見人はどういう制度なのか
見ていきましょう。
スポンサーリンク
成年後見人はどんな制度?

厚生労働省ホームページでは
次のように書いてあります。
成年後見制度とは、
知的障害・精神障害・
認知症などによってひとりで
決めることに
不安や心配のある人が、
いろいろな契約や
手続をする際にお手伝いする
制度です。
障害のある人もない人も、誰もが
尊厳のある自分らしい生活を
続けられ、地域社会へ参加できる
ことを支える「権利擁護支援」。
ニーズが高まり多様化している成年後見制度は
利用している人と同じ目線で考え
相談し合える市民後見人や、長期間にわたり
支援を継続することのできる法人後見の
役割が今後ますます重要になっていきます。
地域の力、ネットワークが生み出す力で
意思と権利が尊重され、地域社会へ参加
する機会が増えるようになるのです。
厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/
成年後見人を出来る人は?
成年後見人になるために特別な資格は
不要です。
成年後見人は、もともと弁護士や
司法書士が行っていました。
認知症の方が増加したことにより
知的障害や、精神障害の方も多いことから
国が市民の方に依頼する事業としても
地方公共団体でも、養成研修を積極的に
行われるようになりました。
成年後見人は家庭裁判所が選定を
します。
本人にとって適任だと判断された方が
成年後見人に選任されます。
財産管理や事情が複雑である場合には
弁護士や司法書士などの専門的な知識を
持っている専門職の人が選ばれる場合も
あります。
ただし下記の人は成年後見人になれません。
– 未成年者
– 破産者
– 過去に成年後見人等に選任されていたが
家庭裁判所から解任された者
– 過去に被後見人に対して訴訟を提起した者
およびその配偶者ならびにその直系血族
– 行方不明者
・市民後見人
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの
資格をもたない、親族以外の市民による
成年後見人等です。
市町村等の支援をうけて、後見業務を
適正にサポートします。
主な業務は、ひとりで決めることに
不安のある方の金銭管理、
介護・福祉サービスの
利用援助の支援などです。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・
技術、社会規範、倫理性を身につけます。
登録後、家庭裁判所からの選任を
受けてから、成年後見人等としての
活動が始まります。
・法人後見
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人
NPO法人などの法人が成年後見等になり
判断能力が不十分な人の保護・支援を
行います。
法人後見では、法人の職員が成年後見制度に
基づく後見事務を担当して行います。
担当している職員がなんらかの
理由で事務を行なえなくなっても
担当者を変更することにより
後見事務を継続して行えるという利点が
ありますよ。
厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/

スポンサーリンク
法定後見制度
精神上の障害(認知症・知的障害・
精神障害など)により
判断能力に欠けているのが
通常の状態にある方を保護・
支援するための制度です。
成年後見人制度を利用すると
家庭裁判所が選任した成年後見人は
本人の利益を考えながら
本人を代理して契約などの
法律行為をします。
本人または成年後見人が
本人がした不利益な法律行為を
後から取り消すこともできます。
自己決定の尊重の観点から
日用品(食料品や衣料品等)の
購入など
「日常生活に関する行為」
については、保佐人の同意は必要なく
取消しの対象にもなりません。
また、家庭裁判所の審判によって
保佐人の同意権・取消権の範囲を
広げたり特定の法律行為について
保佐人に代理権を与えることもできます。
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害
・精神障害など)により、判断能力の
不十分な方を保護・支援するための
制度です。
成年後見人制度を利用すると
家庭裁判所の審判によって
特定の法律行為について家庭裁判所が
選任した補助人に同意権・取消権や
代理権を与えられます。

成年後見制度を相談するには?
成年後見制度を利用したい場合は
下記で行っていますので
相談するとよいでしょう。
*市区町村の高齢者福祉課等
*社会福祉協議会
*地域包括支援センター
*成年後見を業務とするNPO等
自分が一番話をしやすいところで
相談しましょう。
成年後見制度の利用を開始するためには
また、成年後見制度の利用を開始
するためには、家庭裁判所へ手続きを
行う必要があります。
手続き先は、後見を必要としている
本人の住所地を管轄する家庭裁判所と
定められているためどこの家庭裁判所が
管轄しているのかわからない場合は
裁判所のホームページから事前に
確認しておくようにしましょう。
後見開始の手続きができる人は
限られているため注意が必要です。
*本人
*配偶者
*4 親等内の親族
*成年後見人等
*任意後見人
*任意後見受任者
*成年後見監督人等
*市区町村長
*検察官

法定後見制度種類
法定後見制度には、障害や病気の
度合いによって3つの種類が定めらています。
*補助人
重要な手続・契約の中で、ひとりで
決めることに心配がある方
*補佐人
重要な手続・契約などを、ひとりで
決めることに心配がある方
*後見人
多くの手続・契約などを、ひとりで
決めることがむずかしい方
家庭裁判所が選んだ成年後見人は
本人の利益を考慮して保護、
支援をします。
詳しくは厚生労働省ホームページを
ご覧ください。
厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/
まとめ
あなたが病気や障害を負うことに
なっても、国にはあなたをサポート
してくれる制度があります。
安心ですよね。
このような制度があることで
私たちは安心して暮らせるわけです。
私たちがもし病気や障害などで
手続・契約などを、ひとりで決める
ことに心配が出てきた場合
家庭裁判所から選出された
*市民後見人
*法人後見
*法定後見制度
状態に合わせて3つのどれかを
利用することが出来ます。
さらに詳しく知りたい方は
厚生労働省ホームページの成年後見の
わかりやすいページをご覧ください。
厚生労働省
https://guardianship.mhlw.go.jp/
スポンサー


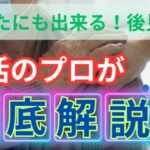


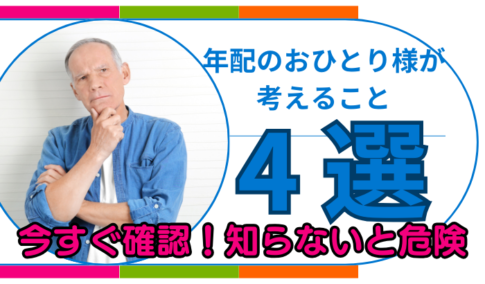

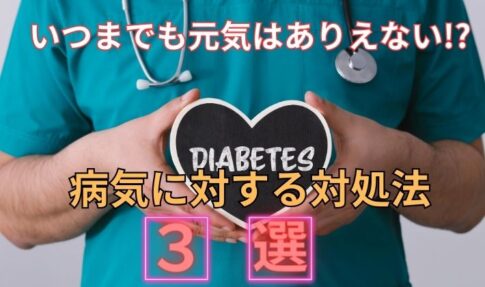




 Users Today : 3
Users Today : 3 Users Yesterday : 4
Users Yesterday : 4 Users Last 7 days : 46
Users Last 7 days : 46 Users Last 30 days : 173
Users Last 30 days : 173 Users This Month : 150
Users This Month : 150 Users This Year : 1070
Users This Year : 1070 Total Users : 1709
Total Users : 1709 Views Today : 3
Views Today : 3 Views Yesterday : 5
Views Yesterday : 5 Views Last 7 days : 158
Views Last 7 days : 158 Views Last 30 days : 726
Views Last 30 days : 726 Views This Month : 649
Views This Month : 649 Views This Year : 4687
Views This Year : 4687 Total views : 7280
Total views : 7280 Who's Online : 0
Who's Online : 0
コメントを残す